1925~1929(大正14~昭和4)年
1925年、日本農民組合千葉県連合会が発会し、8月には、雑誌「房総青年処女(千葉県青年処女)」が創刊されました。関東大震災で崩壊した野崎島灯台(1869年建造)が、新しく生まれ変わりました。京成遊園地(谷津遊園)が開園します。1926年、京成電気軌道の大和田駅が開業し、東京への行商人などで賑わいました。自由教育が広がる一方で、上級学校を目指す生徒による自由教育批判も出始めます。松戸の陸軍工兵学校の演習を皇太子(昭和天皇)が台覧しました。労働争議も多発しました。
1927年9月に始まる野田醤油労働争議は翌年4月に解決し、改善計画が推進されることとなりました。米ギューニック博士から送られた青い目の人形が各地の小学校に寄贈されます。返礼として千葉から二体の人形「ミス千葉」が「房子」が贈られました。この頃から県の農業試験場で落花生研究が始ります。
1928年、成年男子による初の普通選挙(県会議員)で政友会が圧勝します。関東大震災の大津波で被害を受けた中山競馬場が現在地(船橋市古作)に移転します。自由教育の手塚岸衛(大多喜中学校長)は辞職に追い込まれ、東京に自由が丘学園を作りました。
1929年、房総線上総興津・北条線安房長狭間が開通し、房総環状線が全通します。宮脇梅吉、後藤多喜男と知事がかわります。世界恐慌の影響で繭価や米価が急落し、農家の経済を直撃しました。品質の高さで有名であった「行徳の塩」が歴史を閉じます。
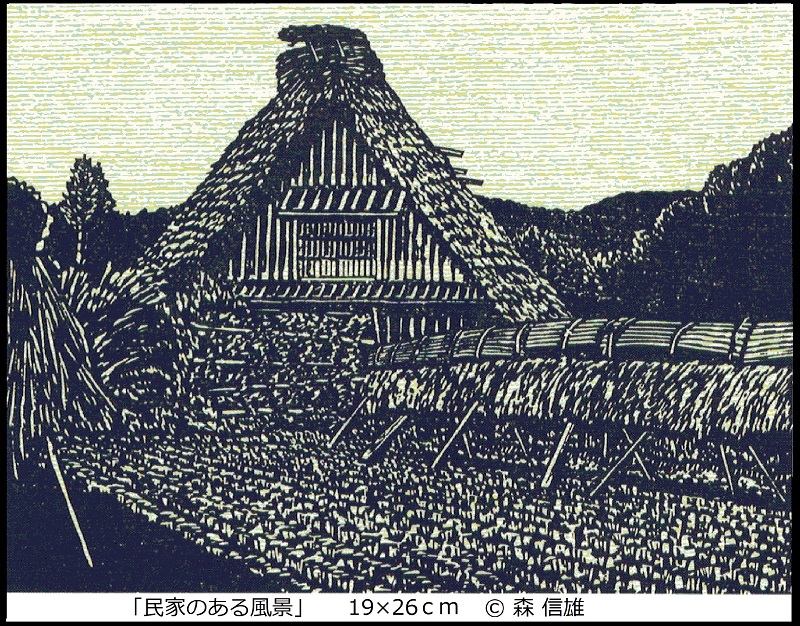
| 西暦 | キーワード |
|---|---|
| 1925(大正14)年 | 「フルーツパーラー」「公衆電話」「ラヂオ」「軍教」「セーラー服」 |
| 1926(大正15/昭和1)年 | 「十勝岳噴火」「円本」「モボ・モガ」「豊田自動織機製作所」 |
| 1927(昭和2)年 | 「大日本相撲協会」「立憲民政党」「シャン」「青い目の人形」 |
| 1928(昭和3)年 | 「張作霖」「ラジオ体操」「マルクスボーイ」「ママさん」「モン・パリ」 |
| 1929(昭和4)年 | 「改造文庫」「エノケン」「えじゃありませんか」「大学は出たけれど」 |
